「集中力が続かない」「忘れ物が多い」「衝動的な行動が抑えられない」そんな日常の困りごとから「もしかしてADHDかもしれない」と受診を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意・多動性・衝動性が日常生活に支障をきたす発達障害の一つで、生まれ持った特性です。診断には医療機関での専門的な評価が求められます。
こちらでは、ADHDの診断を行う専門医や病院・クリニックでの検査方法、診断後に生活で意識したいポイントをご紹介します。
広島でADHDの診断や治療でお悩みの方は、立町クリニックにご相談ください。ADHD(発達障害)を専門外来として扱っており、ADHDの特性や生活上の困難さについて、きめ細かなサポートを行います。日本精神神経学会認定の精神科専門医による正確な診断と、患者様の生活に合わせた最適な治療計画(薬物療法や生活指導など)をご提案いたします。ADHDだけでなく、うつ、不安、不眠などの合併症状についても、心療内科・精神科の視点から総合的に治療いたしますので、まずはお気軽にご来院ください。
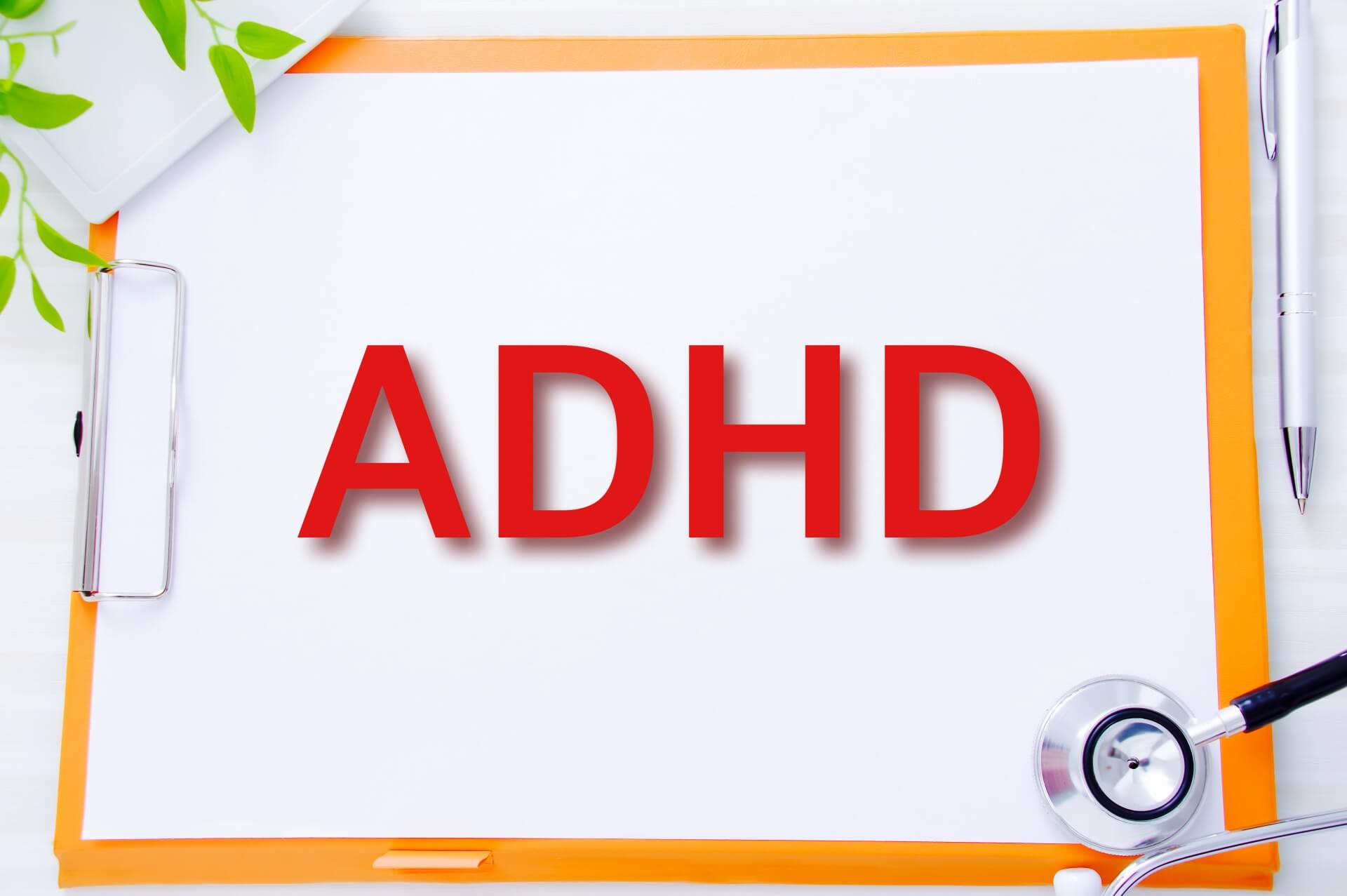
ADHDの診断は、専門的な知識を持つ専門医が在籍する病院やクリニックで行われます。適切な治療や生活サポートを受けるための第一歩として、どのような専門医が診断を行うのかを理解しておきましょう。
ADHDの診断と治療は、主に以下の専門医が担当します。
大人のADHDの診断・治療が中心です。合併しやすい他の精神疾患との鑑別も行います。
ADHDに伴うストレスが原因の心身症状を扱う場合に適しています。
主に子どものADHDの診断・治療を行います。
専門医は、ADHDの特性と他の疾患を慎重に見分ける役割を担います。
ADHDの診断を受ける病院・クリニックを選ぶ際には、以下の点に着目しましょう。
発達障害やADHDの専門外来を設けている病院・クリニックは、診断実績が豊富である可能性が高いです。
精神科専門医など、ADHDを含む精神疾患の診断に精通した資格を持つ医師が在籍しているかを確認することが、信頼できる病院・クリニックを選ぶ基準となります。

ADHDの診断は、血液検査のような単一の検査だけで確定するものではありません。専門医による詳細な問診と、複数の心理検査や行動評価を組み合わせることで、ADHDの特性が生活にどの程度影響しているかを総合的に判断します。
ADHDの診断では、現在の症状だけでなく、子どもの頃からの生活状況や発達経過を詳しく把握するための検査が中心となります。
専門医が本人や家族(または子どもの場合は保護者)に対して、不注意、多動性、衝動性といったADHDの症状が生活のさまざまな場面でどの程度現れているかを具体的に聞き取ります。
質問紙形式の検査で、ADHDの症状の重症度や傾向を客観的に評価します。大人の場合は、成人ADHD診断検査(ASRS-V1.1)などが用いられます。
知的な発達のバランスや、他の精神疾患が合併していないかを確認するために、知能検査や性格検査などを行うことがあります。
病院・クリニックでADHDの診断が下されるまでには、以下のステップを踏みます。
詳細な問診と各種評価スケール、必要に応じた心理検査を行います。
専門医が検査結果、問診情報、これまでの生活歴などの全ての情報を総合的に分析します。
国際的な診断基準(DSM-5など)に照らし合わせ、ADHDの特性が生活に大きな支障をきたしていると判断された場合に診断が確定します。
診断は時間をかけて慎重に行われます。不安な点があれば、専門医に相談しながら進めていきましょう。
ADHDと診断されたことは、生活の困難の原因が明確になったことを意味し、適切なサポートを受けるためのスタートラインに立ったということです。
こちらでは、診断を受けた後の治療の進め方と、日々の生活で実践できるヒントについて解説します。
ADHDの治療は、症状の軽減と生活の質の向上を目指して行われます。
ADHDの治療の中心の一つです。脳内の神経伝達物質の働きを調整することで、不注意や衝動性といった症状を軽減し、生活しやすくする役割があります。専門医が診断に基づき、患者様の生活状況に合わせて慎重に薬を選びます。
ADHDの特性を考慮した生活環境を整えることも重要です。忘れ物対策のためのチェックリストの活用、集中できる環境の整備、タスクの細分化など、生活上の具体的な工夫について専門医や臨床心理士から指導を受けられます。
ADHDの特性を理解し、その特性を活かしながら生活の困難を軽減していくことが大切です。
ADHDの特性は弱点ではなく、「得意なこと」と「苦手なこと」の偏りとして捉え、自己肯定感を保ちながら生活することが重要です。
家族や職場の理解を得ることで、特性に合わせたサポート(指示の伝え方の工夫、仕事の割り振りなど)を受けやすくなり、生活の困難さを減らせます。診断は、周囲に協力を求めるための客観的な根拠となります。
ADHDは慢性的な特性であるため、診断後も継続的なサポートが重要です。
専門医は、治療の効果や生活上の変化を定期的に評価し、治療方針の調整や生活指導を継続的に行う役割があります。
必要に応じて、地域の支援機関や就労支援サービスなどの社会資源の紹介を受け、生活全体のサポート体制を築くことができます。
| 院名 | 立町クリニック |
|---|---|
| 住所 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2-2立町中央ビル6F |
| TEL | 082-247-6767 |
| FAX | 082-247-0555 |
| URL | https://tatemachi-clinic.jp |
| 診療科目 | 内科・心療内科・神経科・精神科・うつ・不眠・禁煙外来・むずむず脚症候群外来・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・ADHD |
| 診療時間 | 9:00〜12:30 15:30〜18:00 |
| 休診 | 水曜日・土曜日の午後 及び、日曜日・祝日 |
| アクセス | 広電、立町電停より徒歩1分。 新生銀行向い八丁堀バス停より徒歩3分。 ビルの1階は、牛丼の「すき家」です。 |